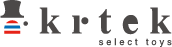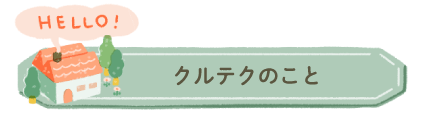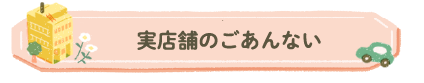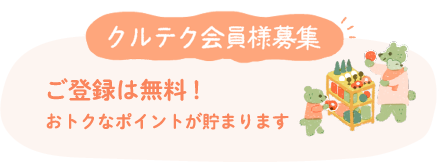地球温暖化を少しでも食い止めるためにプラスチックの使用を減らそうという動きは、ヨーロッパの方が早いです。輸入されてくる品物からどんどんシュリンクが外されていることからもわかります。現地へ行ってみれば、本当に使わないようにしているんだなと至るところで感じます。
今回4つの国を歩いたわけですが、特に、プラスチック、見た?と思うほど脱プラだったのはエストニアでしょうか。陶器をいくつか購入しましたが、プチプチではなく段ボールシートでくるみ、セロテープではなく紐で結んで渡してくれました。これが、プラスチックのプチプチよりしっかり品物を保護してくれて、無傷で日本に持ち帰ることができたのです。デンマークでは薄い紙を何枚も重ねて壊れ物をくるんでくれましたね。やはりプチプチではなかったです。店でもさっそく段ボールシートを導入しました。品物によりますが、なるべくビニール製品ではないもので保護することに挑戦してみたいと思っています。なお、エストニアは、世界屈指のIT先進国との事で、中世の風景の中で進んだキャッシュレス仕様でした。
シュリンクがないことで、箱にはスレができやすくなります。少し前は、箱のスレにも指摘をいただいておりました。木目や木目による塗装の色ムラなども不良品としてお申し出がありました。店内では、不本意ながらプラスチックを多用しています。商品保護には最適なのです。シュリンクなしで入荷するものにもわざわざかけていることもあります。そうしないと選んでいただけないことは多々あります。子どもさん、どうしても商品に触れてしまうので、やはり保護は必要、となります。
日本人がきれい好き、清潔なのは、住んでいて非常にありがたいことです。なので、商品に対して潔癖ではなくなることと両立するのはなかなか難しい。
北欧のカフェで、紙ストローは嫌だなーと思いながら、取り組みの顕著な違いを感じたときにいろいろ考えました。